こんにちは、シロロです。
今回は、粘土遊びシリーズ第4弾「平らにしよう!」です。
「粘土をドスン!」「ベチャッ!」
この音が聞こえると、なんだかワクワクしませんか?
今日はそんな、全身を使って粘土を“感じる”遊びについて話していきます。
ドスン!からはじまる遊びの世界
子どもたちは、やわらかい粘土のかたまりを手にすると、
持ち上げてはドスン!と台に落とします。
「うわぁ、ペタンコになった!」
「ホットケーキみたい!」
そう言いながら何度も繰り返す姿は、まさに夢中そのもの。
音や手ごたえを楽しむ中で、自然と力の加減を学んでいます。
全身を使うって、実はすごいこと
「たたく」「押す」「のばす」――
これ、ただの遊びじゃありません。
粘土をたたく動きには、
手だけじゃなく、腕、肩、体幹までも使われています。
つまり、全身のバランス感覚や力のコントロールを養っているんですね。
子どもって遊びの中で、ちゃんと自分の身体を使う練習をしてるんです。
道具を使うことで広がる発見
手で叩いたあとに、丸い棒(めん棒)を渡してみると……
「つるつるになった!」「こっちの方がキレイ!」
粘土の“のばし方”にも違いがあることに気づきます。
この発見こそ、次の創作意欲につながるんです。
型押ししてみよう!新しい発見がうまれる遊び
平らに伸ばした粘土の上に、いろんな器具を押し当ててみると…ほら、形がつく!
スプーンの裏、ボタン、積み木の角やキャップなど、なんでも“型押し道具”に早変わり。
押すたびに、指先に心地よい抵抗が伝わってきます。
「お花みたい!」「顔に見える!」など、偶然できた形がイメージを広げ、
そこから顔づくりや模様づくりへと自然に発展していきます。
この型押し遊びは、形を見つける力や並べ方を工夫する感覚を育てる活動です。
思わぬ発見や偶然の面白さを共有することで、子ども同士の会話や協同も生まれます。
量への配慮が、子どもの表現を広げる
保育でよくあるのが、粘土の量が少なすぎるパターン。
これだと、指先だけの遊びに終わってしまって、
「のばす」「たたく」といったダイナミックな動きが出にくくなります。
子どもの想像が広がるように、たっぷり使える粘土量の確保を意識しましょう。
「こちらの記事もおすすめ」👇️
✴️【4・5歳児 泥粘土でダムをつくろう!】https://shiroronblog.com/damu/
まとめ|「平らにする」は表現の入り口
粘土を平らにする動きの中には、
「感触を味わう」「音を楽しむ」「力を調整する」「形を変える」
という、たくさんの“学び”が詰まっています。

子どもが思いきり手を動かせる環境を整えて、
「つくるって楽しい!」という気持ちを育てていきましょう。
🌷次回の【粘土で育つちから Vol.5】は「ひも状にのばそう!」。https://shiroronblog.com/himojiyou/
粘土をヘビのように転がしていく姿から、友だちとの関わりや想像力の広がりを見ていきます。
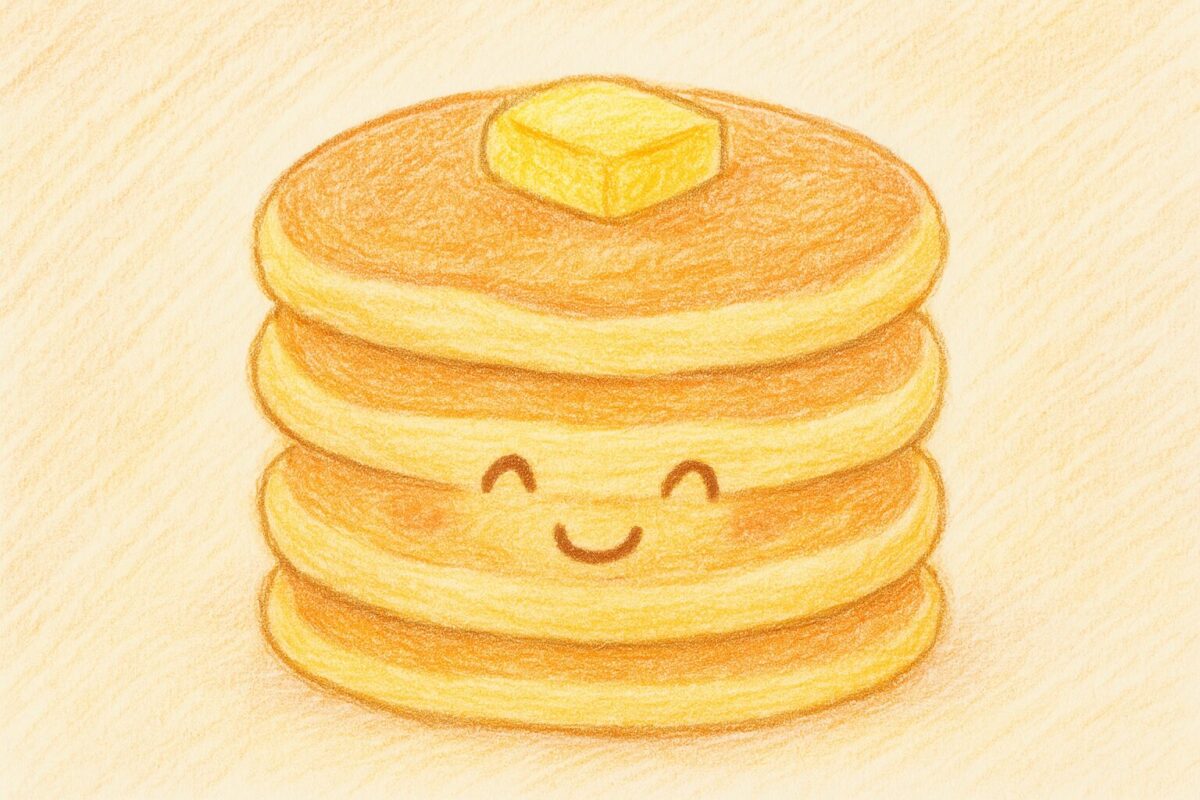


コメント