こんにちは、シロロです。
今日は「子どもたちが生き生きと表現するための保育環境」についてお話しします。
絵を描く。歌をうたう。踊る。話す。つくる。
子どもたちが夢中になる姿は、見ているだけで胸があたたかくなりますよね。
でも、あの“生き生きさ”はどこから生まれるのでしょうか?
その答えは――
「子ども自身が主体的に生きている毎日」 にあります。
教える時間が増えるほど、子どもの時間が減る
最近、保育の現場では
「英語の先生」「リトミックの先生」「絵の先生」など、
専門家が短時間ずつ担当する“ぶつ切り保育”を見ることが増えてきました。
パッと見は効率的で、整っているように見えます。
でも、子どもたちは“専門家になる練習”をしているわけではありません。
子どもが絵を描くのは、「表したい思い」があるから。
歌をうたうのは、「気持ちを届けたい」から。
「教わるための時間」ではなく、
「自分で感じて、動き出す時間」こそが、本当の学びを生み出します。
今の子どもたちは「体で学ぶ」機会が減っている
外で夢中になって走る。
泥んこになって遊ぶ。
ちょっとした“いたずら”をきっかけに発見する。
そんな「体で学ぶ経験」が、確実に減っています。
安全のため、効率のため、ルールのため――
大人の都合で、子どもの「やってみたい!」を止めてしまう場面も増えていませんか?
でも、実はその小さな「やってみたい!」の中に、
表現の芽が隠れているのです。
「こちらの記事もおすすめ」👇️
✴️4.5歳児泥粘土でダムをつくろう!https://shiroronblog.com/damu/
幼児期は“芸術年齢”
幼児期は、感じたことをそのまま素直に表現できる、特別な時期です。
この時期に育つ
「感じる力」や「表す力」は、一生の土台になります。
個性も発達も違う子どもたちが集まると、
刺激したり、真似したり、工夫したりしながら成長していきます。
その中で生まれる姿こそ、
本物の学びのプロセスです。
造形表現は“心の記録”
子どもの描いた絵や作ったものは、ただの作品ではありません。
そこには
「今、その子が何を感じ、どう生きているか」
がまっすぐに表れています。
つまり造形表現は、
子どもの心の記録なのです。
大人がそこから学べることは、実はたくさんあります。
「こちらの記事もおすすめ」👇️
✴️子どもの絵から見える心と発達https://shiroronblog.com/enosodati/
まとめ:子どもが“自分で動き出す”環境を
子どもたちが生き生きと表現できる保育環境とは、
決して「大人が教え込む場」ではありません。
それは、
子どもが自分の思いで動き出し、感じ、表現できる環境 のこと。
忙しい今の時代だからこそ、
子どもたちにとって本当に必要な「時間」や「体験」について、
もう一度立ち止まって考えたいですね。

「子どもが主体的に生きる毎日」こそが、
生き生きとした表現活動のいちばんの土台です。
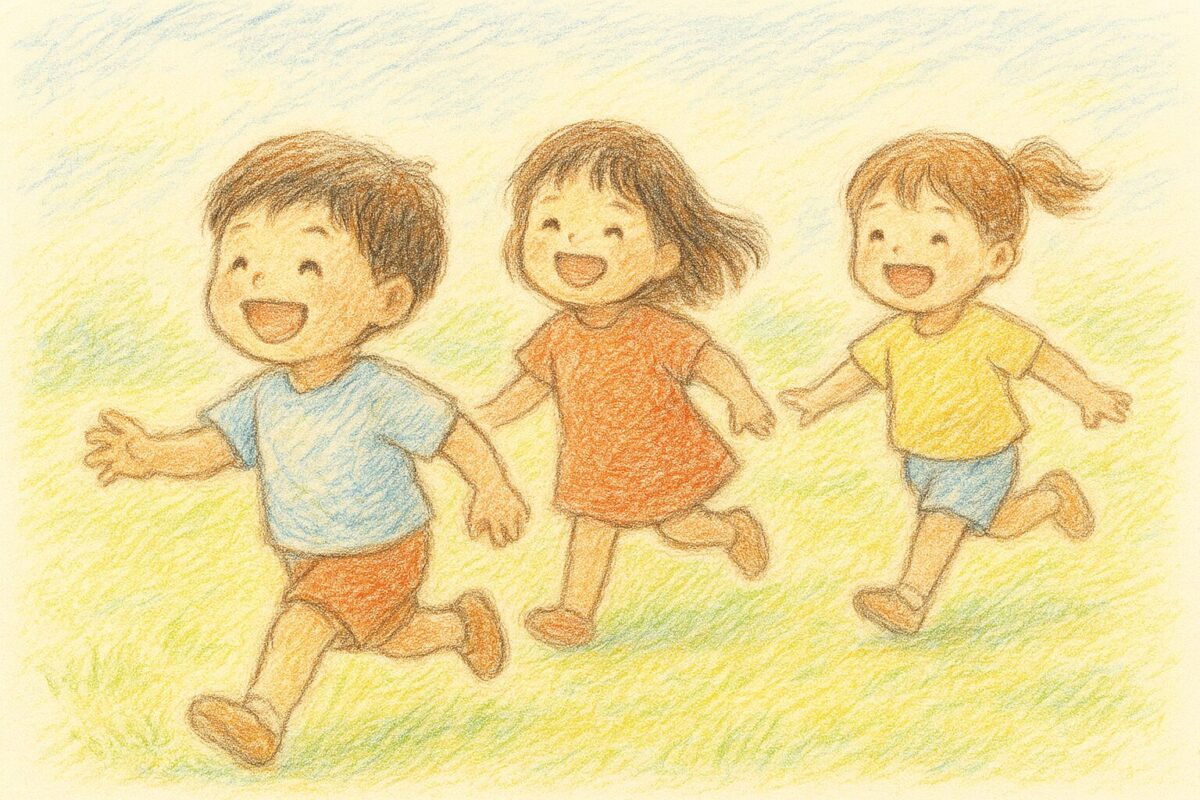


コメント