― 運動のあとに生まれる「貼り絵」という表現 ―
こんにちは、シロロです。
今回は、体を使った経験のあとに生まれる表現活動についてお話しします。
テーマは「貼り絵」。
けれどこれは、ただ作品を完成させるための制作活動ではありません。
子どもが体で感じ、心を動かした経験を、
もう一度見つめ直すための大切な時間です。
体を動かした経験は、心の中に残り続ける
走った、跳んだ、転んだ、笑った。
体を思いきり使った経験は、子どもの中に確かな実感として残ります。
その実感が、
「思い出したい」「表したい」という気持ちを生み、
次の表現へとつながっていくのです。
ところが、今の生活ではどうでしょう。
大人も子どもも、体や手足を使って動く時間が、年々減っています。
実はこれは、幼児期の発達にとって大きなマイナス。
体を動かす経験は、思考力や感情、人と関わる力の土台になります。
だからこそ、保育の中で
「体を使う経験」を意識的に保障することが欠かせません。
貼り絵は「上手につくる」ための活動ではない
ここで取り組む貼り絵は、
手先を器用にするための練習ではありません。
目的は、
自分の経験を思い返し、表そうとする力を育てること。
紙は、破いたり、切ったり、動かしたりできる素材。
描く表現とは違い、
「こうしたい」と思ったら、何度でも試し直すことができます。
このやり直せる余白こそが、
子どもに安心感と挑戦する気持ちを与えてくれるのです。
実践① 運動会のあとに取り組んだ貼り絵
運動会を終えたあと、
子どもたちは自分たちの経験を貼り絵で表現しました。
- 5歳児:縄跳び・リレー
- 4歳児:ダンス
「腕って、どう動いてた?」
「走るとき、足はどっちに出る?」
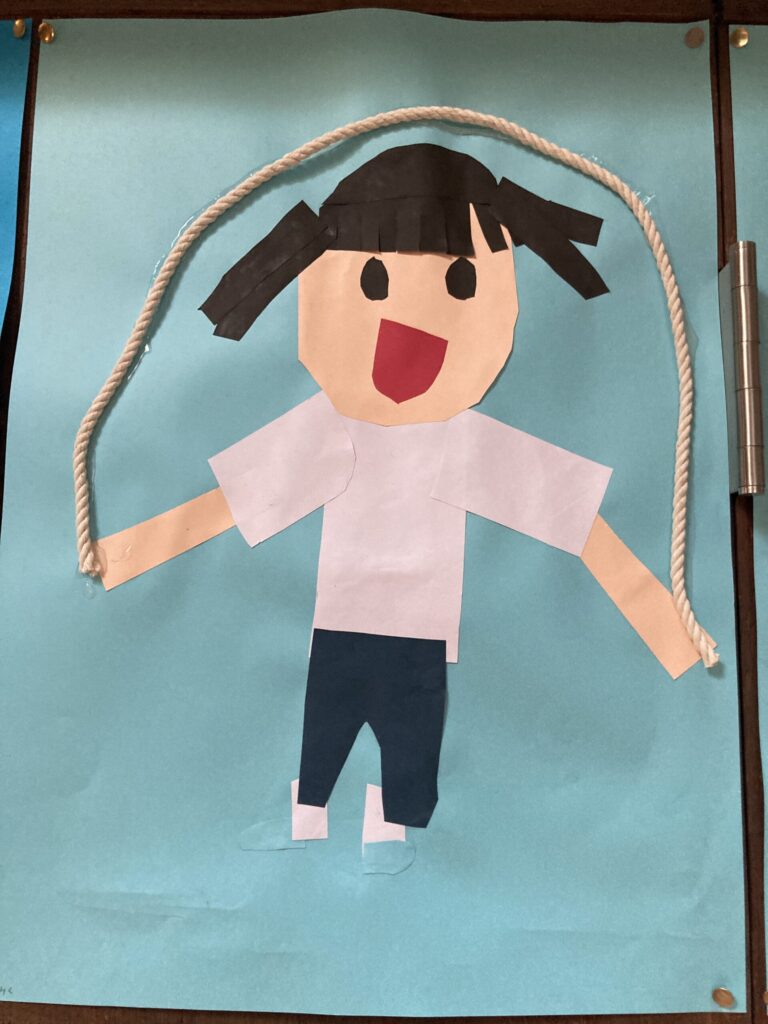
自分でポーズを取ったり、友だちや先生の体を見たりしながら、
動きを一つひとつ確かめていきます。
体を思い出し、紙を切り、貼り、動かす。
そこには、経験をじっくり振り返る時間が流れていました。
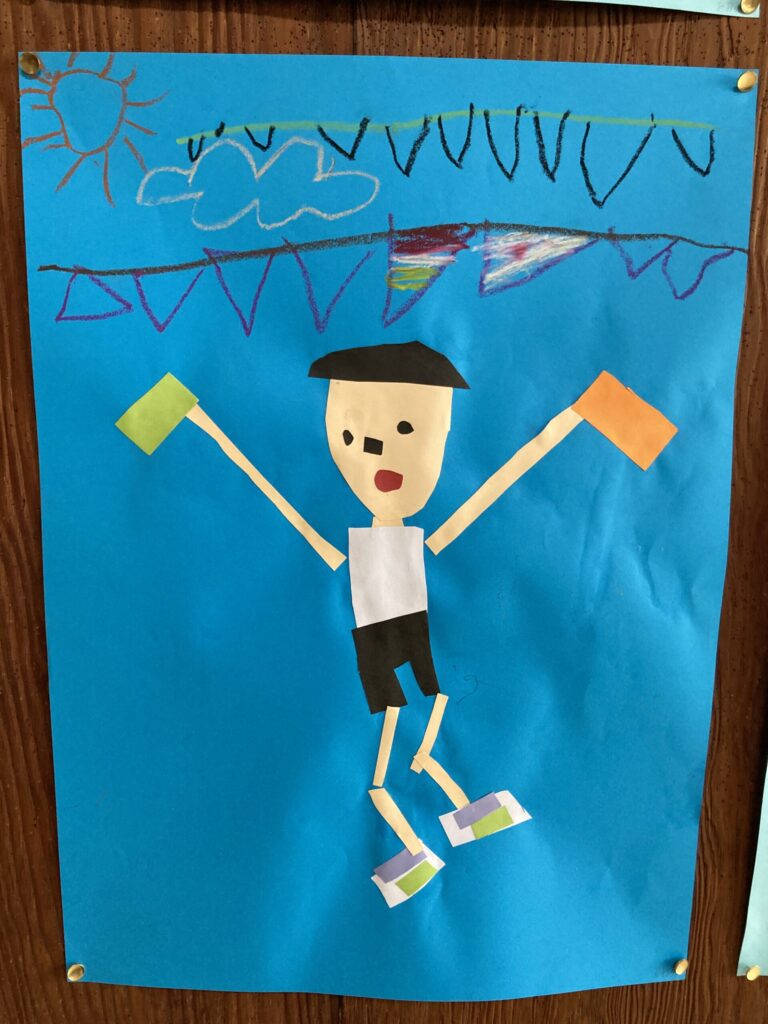
実践② 玉入れを“みんなで”表現したクラス
別の4歳児クラスでは、
玉入れの様子を大きなロール紙に貼り絵で表現しました。
このクラスは、練習当初はなかなか勝てず、
最初は玉が2つしか入らなかったそうです。
それでも、練習を重ねるうちに少しずつ上達し、
本番前には、もう1クラスといい勝負に。
「負けたくない」
「今度こそ入れたい」
そんな思いを胸に投げ続けた経験が、
貼り絵の中に生き生きと表れていました。
結果は惜しくも負け。
それでも子どもたちは、
「がんばったこと」「みんなで力を合わせたこと」を
しっかりと感じ取っていたのです。
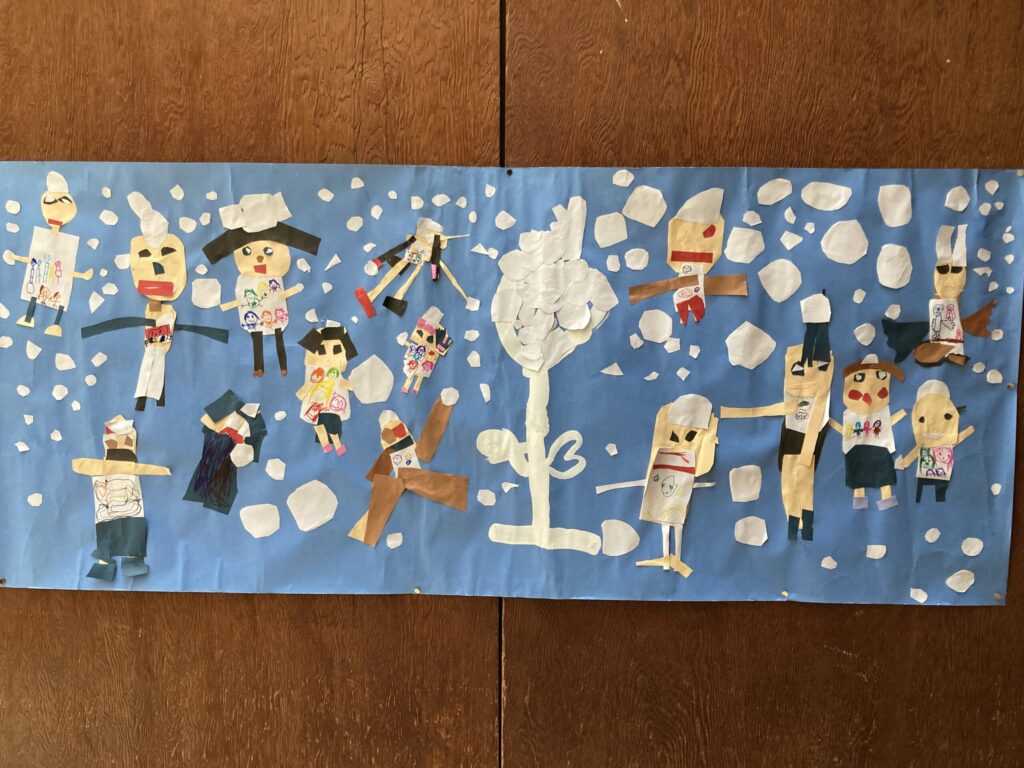
貼り絵は“動きの表現”を支える道具
人の動きを絵で表すのは、難しく感じる子もいます。
でも貼り絵なら、体をパーツとして考えられる。
- 頭はここ
- 腕はこの向き
- 足は曲がっているかな?
試して、動かして、やり直す。
失敗を恐れずに挑戦できることが、
貼り絵の大きな魅力です。
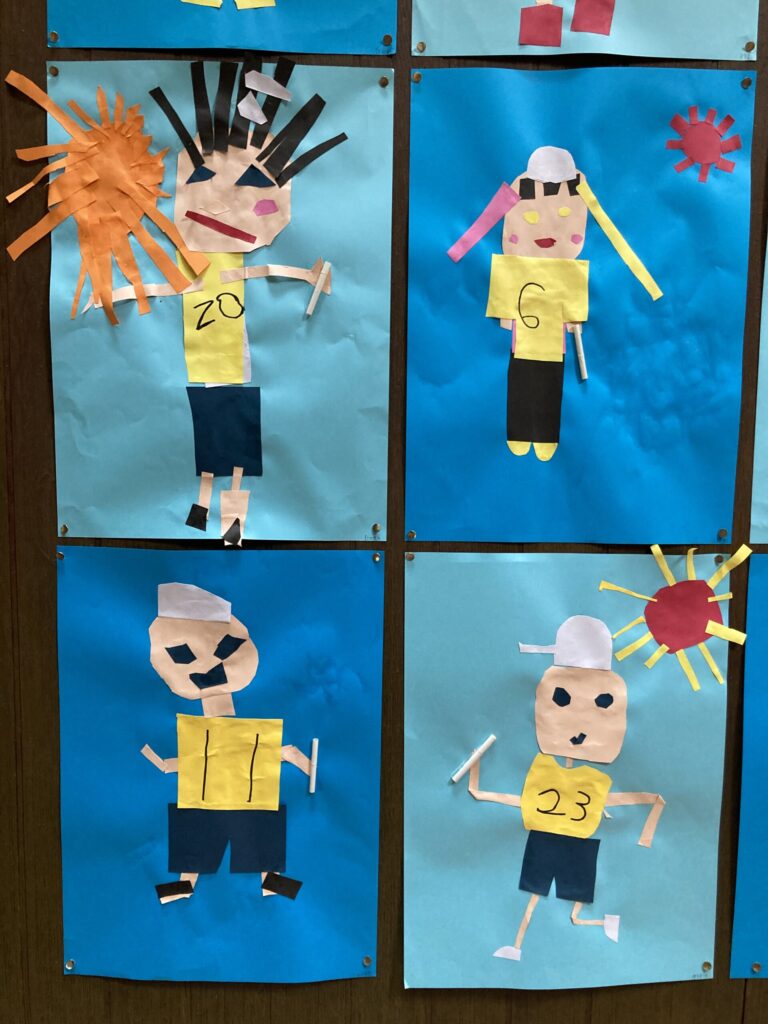
「こちらの記事もおすすめ」👇️
✴️身近な素材で心をひらく紙あそびが子ども表現力を育てるhttps://shiroronblog.com/kamiasobi/
✴️ハサミ遊びー初めての「切る」体験https://shiroronblog.com/hasami/
まとめ:表現は、心と体が動いてこそ生まれる
人や物、出来事の関係を表現することは、
子どもの認識を大きく広げます。
けれど、その前提として必要なのは、
心と体がしっかり動く経験。

感じて、動いて、振り返り、表す。
このサイクルを大切にすることこそ、保育の本質なのだと感じています。
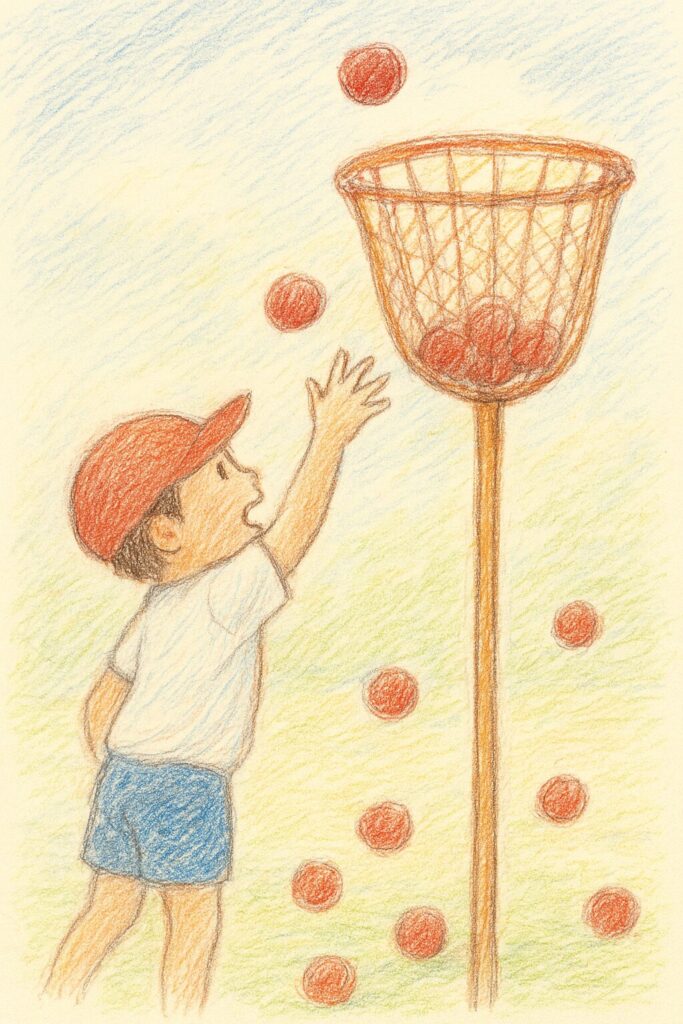


コメント