〜小さな命から学ぶ、心と表現の育ち〜
こんにちは、シロロです。
梅雨の季節、しとしと雨の日が続くころ。
園庭を歩いていると、葉っぱの上でのんびり動くカタツムリに出会います。
「わぁ、見て!つのが出た!」
「さわったら、ひっこんだー!」
こんなやり取りが聞こえるのが、梅雨の風物詩です。
生き物は“反応してくれる”存在
カタツムリは、見ているだけでも不思議がいっぱい。
にんじんを食べたら赤いフンをするし、夏には殻の口を膜でふさいで乾燥を防ぎます。
冬になると、落ち葉の中に潜って冬眠。
子どもたちは、そんな様子を観察しながら気づきます。
「生きてるんだね」
そう、生き物は働きかければちゃんと反応してくれる。
この“反応”が、子どもたちの心をぐっと惹きつけるんです。
カタツムリから表現活動へ
カタツムリの名前は”ツムちゃん”
どのカタツムリも”ツムちゃん”
仲良しになったところで、3歳児のクラスで先生が言いました。
「今日は、カタツムリの”ツムちゃん”を描いてみよう!」
4ツ切の白い画用紙と絵の具を用意して、筆を手にした子どもたち。
でも先生は、「カタツムリを上手に描こう」とは言いません。
目的は“描くこと”ではなく、“筆を動かして楽しむこと”。
最初はカタツムリを描こうとしていた子も、
そのうち夢中でぬたくり始めて、「ママの顔〜!」なんてイメージが変わっていく。
それでOK。
のびのびと筆を動かすことができたら、それだけで十分なんです。
「今日はカタツムリを描いて。っていったでしょ!」なんて言わないでくださいね。笑
👇️3歳の子が描いたカタツムリ(絵の具)
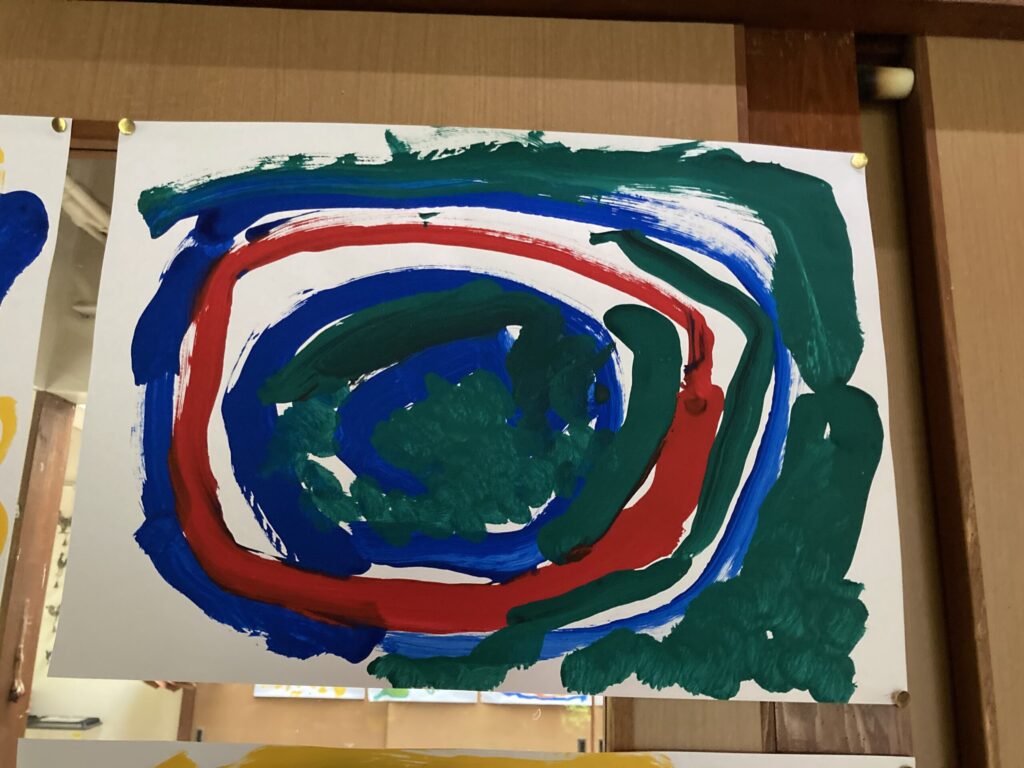
年齢に合わせて、画材もステップアップ!
3歳は絵の具で思いっきりぬりぬり。
4歳になるとクレパスでカタツムリの模様や色を楽しみます。
5歳ではサインペンを使って「おしゃれなカタツムリ」を想像して描く子も。
年齢が上がるにつれて、手先が器用になり、イメージを細かく表現できるようになります。
それを“育ち”として見守ることが大切。
大切なのは「上手さ」より「感じる心」
生き物の知識が増えることよりも、
「命を感じる」「やさしい気持ちを持つ」ことが大事。
観察して、世話をして、描いてみる。
その繰り返しの中で、子どもたちは自然と“思いやり”を学んでいきます。
園の生活って、こういう小さな積み重ねが宝物なんです。
「こちらの記事もおすすめ」👇️
✴️子どもの絵から見える心と発達https://shiroronblog.com/enosodati/
✴️カイコの観察”命のふしぎ”を体感できる最高の教材https://shiroronblog.com/kaiko/
まとめ:感じることから、育つ
カタツムリののんびりした動き。
反応してくれる面白さ。
それを見つめる子どものまなざし。

「生きてるって、すごいね」
そんな気づきが、心の根っこを育てていきます。

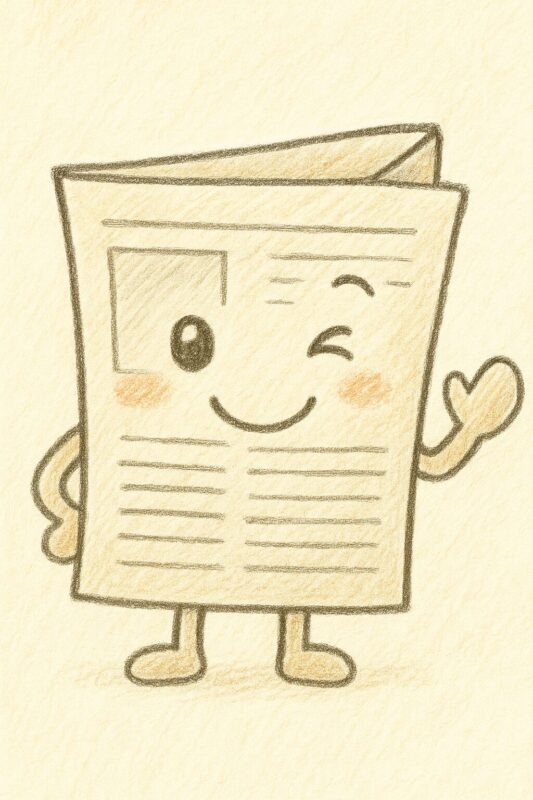

コメント