こんにちは、シロロです。
保育士さん・幼稚園教諭のみなさん。
日々子どもたちと向き合っていると、ふと 「この子はどんなふうに育っていくんだろう?」 と考える瞬間、ありますよね。
「幸せに生きてほしい」
その願いは、先生も保護者も同じです。
だからこそ、幼児期の毎日は“人生の根っこ”を育てる大切な時間。
その子らしい育ちを支えるためにも、 「子どもの絵」には心と発達のヒントがぎゅっと詰まっている んです。
🎨子どもの絵は“心の言葉”
園では子どもたちが毎日のように絵を描きますよね。
でも実は、幼児の生活そのものが造形表現です。
「幼児画は幼児の言葉であり、心の表し」
と言われるほど、描かれた線や丸にはその子の感情や経験が映り込みます。
ところが現場では、
- 先生が見本を描いてしまう
- 「まず丸、その上に三角ね」と説明しすぎる
こんな“描かせる”場面も少なくありません。
これでは、子どもが 「描きたい!」 という内側のエネルギーを受け止めきれず、
どの子の絵も同じようになってしまいます。
大切なのは、
子どもの心の表現を奪わないこと。
🎨共通!「頭足人(とうそくじん)」が示す発達
子どもの絵でよく登場する 頭足人(とうそくじん)。
頭から手足がにょきっと出ている、あのユニークな人の絵です。
実はこれ、国や文化を問わず 世界中の子どもが描く んです。
つまり、表現の形は違っても 発達の道すじは共通 ということ。
頭足人が出てきたら、
「今は“胴体”の概念がまだ育っていない時期なんだな」
と理解できます。
これこそが 絵から発達を見るという視点です。
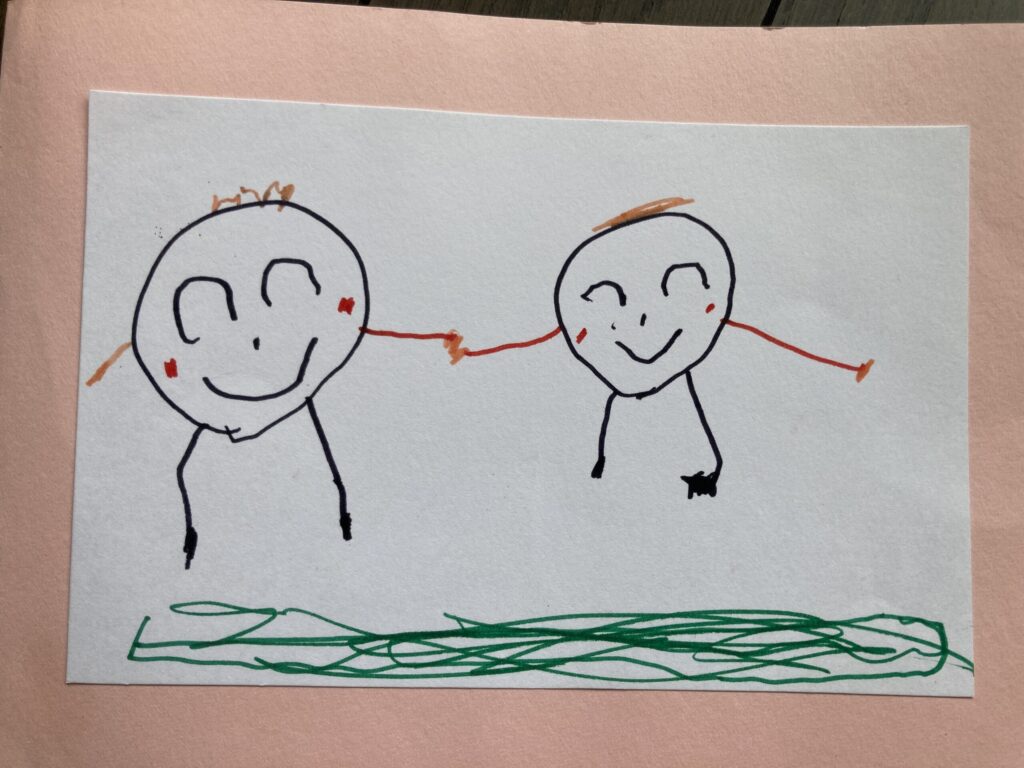

この絵を描いた子は、4歳男の子。地面との境界は認識しているけど、頭足人。個人差ありますよね〜。でも、お顔がニコニコ。心が安定しているのを感じます
🎨年齢ごとの絵の発達(ざっくり)
● 1〜2歳
まだ“何かを描く”という意図はなく、
グルグル・シュッと描いて「痕跡を残す」こと自体を楽しむ。
● 2〜3歳
描いたあとに「これはママ」など意味づけが始まる。
線や丸にストーリーが宿る。
● 3歳〜
頭足人が多く見られる。
「人を描きたい!」という思いが表れやすい時期。
● 4歳〜
実際の見え方よりも “知っていること” を描くようになる。
地面の線(ベースライン)が登場し、世界に境界が生まれる。
🎨園での実例:「ぬたくり」から始まる自由表現
私たちの園では、まず 心の緊張をほぐすために“ぬたくり遊び”からスタート します。
絵の具、クレパス、チョーク…
日替わりで色々な画材をとにかく自由に。
外で大きな紙に描いたり、段ボールをキャンバスにしたり。
手に塗る子もいるけれど、それも立派な表現。
「汚れるからダメ」は言いません。
まずは 表現の楽しさを全身で味わう ことが大事だからです。
生活とつながると、絵は深まる
たとえば——
・ダンゴムシを触ったあとに描くと、足の数までこだわる
・園のチャボやネコは、特徴がしっかり再現される
・季節の草花(ヒガンバナやドクダミ)は色の重ね方が豊かになる
生活→体験→表現
この循環が、子どもの絵をぐんと豊かにします。
「こちらの記事もおすすめ」👇️
✴️チャボの世話で育つ命と感性|鳥小屋当番から広がる保育の学びhttps://shiroronblog.com/tiyabo/
✴️春の園庭で出会うダンゴムシhttps://shiroronblog.com/dangomushi/
● 実例:4歳児が持ってきたイガ栗
「痛い!」と感じたその瞬間の体験が、
絵の具のタッチにそのまま出ることもあります。
絵は、その子の“今を生きる感性”の記録なんです。
👇️4歳の子がイガ栗を持ってきた。
触ってみてとげとげが痛かった!と感じたようです(絵の具)
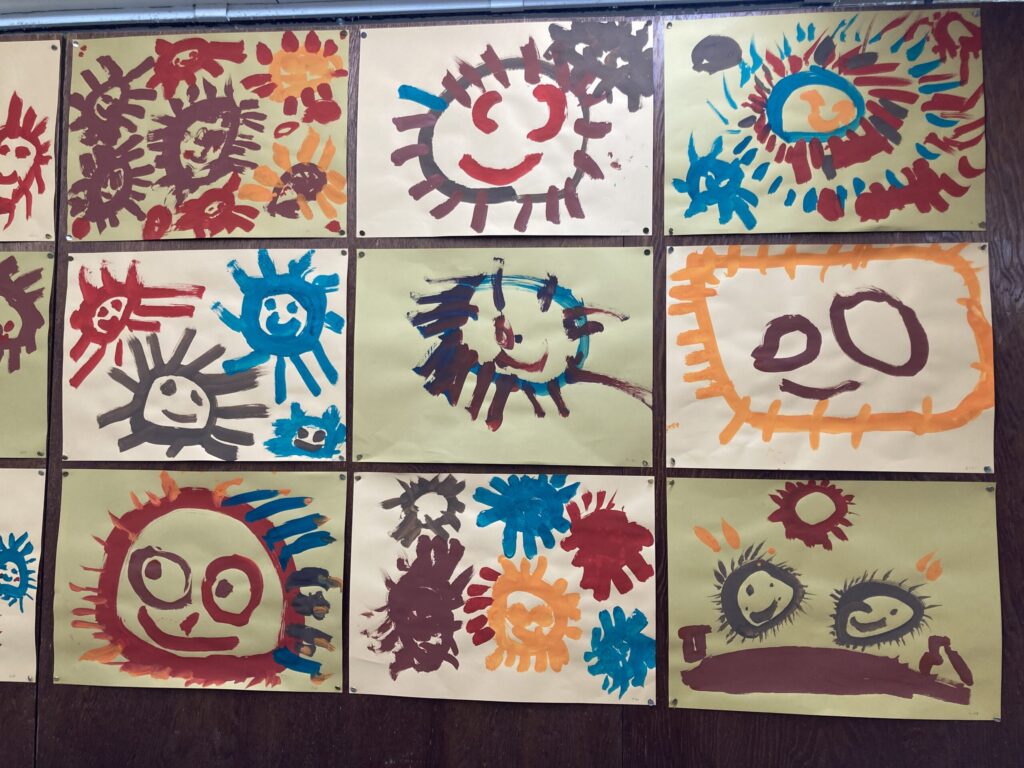
🎨まとめ:子どもの絵は“心と発達のログブック”
子どもの絵は、ただのお絵描きではありません。
心の動きや発達段階がまるごと記録されている大事な表現です。
だからこそ、
「上手に描かせる」よりも
“その子のまま” を受け止めることが何より大切。
絵を発達の視点で見られるようになると、
毎日の保育がもっと面白くなりますよ。

今日も、子どもたちの表現が輝きますように。



コメント