こんにちは、シロロです。
子どもの大切な時期をどう支えるか?
今日は「幼稚園や保育園の働き方を見直そう」というテーマで話していきます。
結論から言うと――
先生が元気で笑顔じゃないと、子どもにとっていい保育はできない!
これに尽きます。
でも現場ではどうでしょう?
行事や準備、書類に追われて毎日残業。寝不足で「今日も疲れたな…」「楽しくないな…」なんて思ってしまう先生も多い。
これじゃあ本末転倒なんですよね。
行事は「子どものためになるか?」で選ぼう
まず見直したいのが行事。
「伝統だから」「毎年やってるから」っていう理由で続けてませんか?
例えば「節分の豆まき」。
子どもによっては鬼が怖すぎて「園に行きたくない!」ってなることもある。
それって子どものためになってないですよね。
私の働いている園では、そういう行事は思い切ってやめてます。
「家庭でやれば十分だよね」という考え方です。
行事を減らすと、日常の遊びや生活にゆとりができる。
その時間を使って、子どもとの関わりを深められるわけです。
お飾りづくりはやめよう
次にお飾り。
「やめたら保育室がさみしくなるんじゃ?」と思うかもしれません。
でも安心してください。
子どもたちが作った作品を飾るだけで、部屋はすぐににぎやかになります。
- 絵の具やクレパスで自由にまたは動物や野草を表現
- 子どもが帰ったあと先生が壁に貼る
これだけで翌日、子どもたちは大喜び。
「これ〇〇ちゃんのだよ!」なんて友達同士で盛り上がります。
先生が夜遅くまで残ってお飾りを作るよりも、笑顔で元気に保育してくれる方が子どもにとっては何倍も価値があるんです。
👇️3歳児お母さんの顔(絵の具)

保育の本質は「毎日の小さな関わり」
幼児期の子どもは「自ら育つ力」を持っています。
その力を引き出すのは、派手な行事や飾りじゃなくて、日々の関わり。
子どもは大人を困らせる行動もしますが、そこで「どう伝えたら動いてくれるか?」を工夫するのが保育者の腕の見せどころ。
小さなやり取りの積み重ねが、子どもの育ちを支えていくんです。
「こちらの記事もおすすめ」👇️
✴️親と先生がすれ違う理由と信頼関係を育てるために大切なことhttps://shiroronblog.com/shinraikankei/
最後に
園によって考え方はさまざまです。
もし「楽しくない」「子どもも生き生きしていない」と感じるなら、その園は自分に合っていないのかもしれません。
他園を見学してみるのも全然アリ。
先生も子どもも笑顔で過ごせる園は必ずあります。

大切なのは、先生自身が元気でいること。
そうすれば、子どもとの時間はもっと楽しくなりますよ。
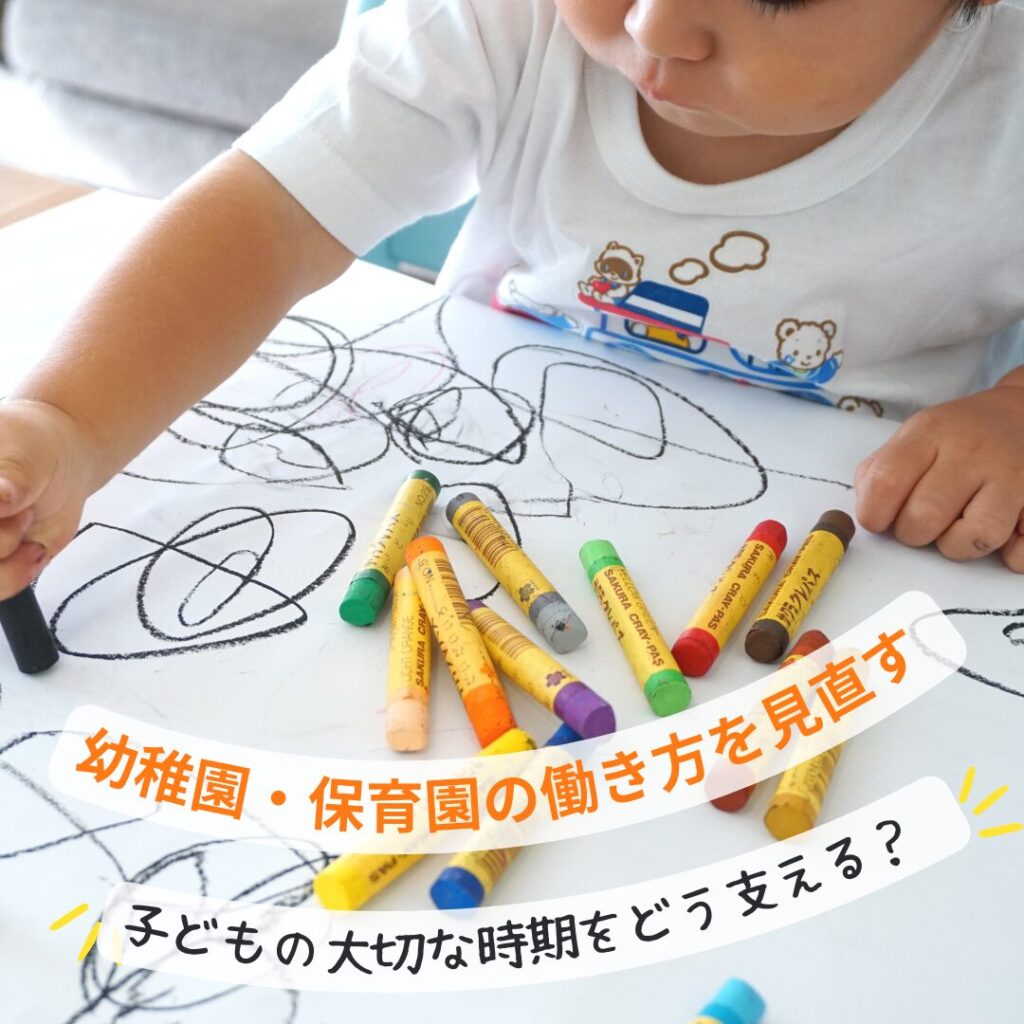


コメント